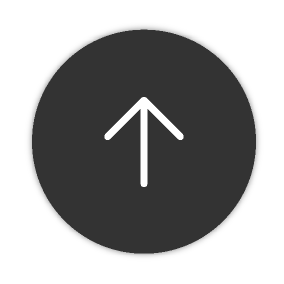放射線検査を受けられる方へ
2022年03月28日
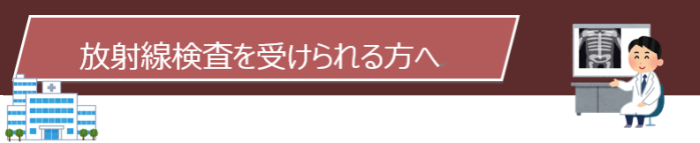
はじめに
放射線検査は体内の状態を可視化することで、病気の診断や治療の方針、効果判定に役立ち、患者さんに大きな利益をもたらします。一方放射線を使うことによる被ばくというリスクも存在し検査を不安に感じる方も多いと思います。
しかし、どの検査にもメリット・デメリットが存在します。
放射線被ばくをむやみに恐れるのではなく、正しく理解した上で検査を受けることが大切です。
医療に使われる放射線について
放射線の種類(※赤字:当院で使用する放射線)
放射線にはX線、α線、β線、γ線、電子線、陽子線等の種類があります。
医療現場ではその特性を生かし以下のような活用が行われています。
| レントゲン検査/マンモグラフィー/骨密度検査/CT検査 透視検査(胃バリウム検査等)/血管造影検査/IVR治療 |
・・・・・・ | X線 |
|---|---|---|
| RI検査 | ・・・・・・ | γ線 |
| 放射線治療 | ・・・・・・ | 高エネルギーX線 電子線、陽子線 |
放射線の単位
放射線の単位は3つあります。
■Bq(ベクレル)・・・・・・放射能量
放射性物質が1秒間に放射線を放つ力のことで、放射能に使われる単位です。
■Gy(グレイ)・・・・・・吸収線量
放射線が、ある物質に当たって吸収された放射線エネルギー量の単位です。
■Sv(シーベルト)・・・・・・実効線量、等価線量
人体への影響を表わし、どの種類の放射線を浴びたか、また各臓器・組織により放射線への感じ方が異なるためそれぞれが持つ感受性などを考慮した数値を使って表した値です。
放射線、放射能の単位を雨に例えると
- Bq(ベクレル)・・・・・・1秒間に降る雨粒の数
- Gy(グレイ) ・・・・・・体にあたって濡れた雨の量
- Sv(シーベルト)・・・・・雨に濡れた影響
放射線検査における被ばく量とその影響
放射線が人体に与える影響については「確定的影響」と 「確率的影響」の二つに分けて考えられています。
「確定的影響」(白内障・不妊・脱毛など)
ある一定以上の放射線を受けなければ現れてこない白内障・不妊・脱毛など人体への影響のことを確定的影響といいます。その影響が現れる一定量をしきい値といいます。
しきい値は、その影響が認められる下限値(影響が 出始める)となります。
しきい値以下の線量では、被ばくしても発生確率はほぼゼロです。 通常の放射線検査でこのしきい値を超えることはありません。
「確率的影響」(発がんや遺伝的影響)
一定量の放射線を受けても、必ずしも現れるわけではなく、放射線を受ける量が多くなるほど現れる確率が高まる影響をいいます。 発がんや遺伝的影響については、放射線の影響なのか自然発症なのか見極めが難しいため、 しきい値がないと仮定さています。
しかし、原爆被ばく者を対象とした疫学調査では、100mSv以下の被ばくでは、がんの発生確率は ほとんど増加しないということが分かっています。
※詳しい線量については別図参考にしてください。
※放射線検査でこのような影響を心配する必要はありません
放射線検査におけるベネフィット(利益)とリスク(不利益)
放射線検査により、多くのベネフィットを得ることになりますが、一方で医療被ばくというリスクも存在します。しかし医療行為 のすべてにリスクは存在します。
逆に、医療を受けないという選択にもリスクは存在します。 患者さんへの放射線の利用はベネフィットが十分に大きい時にのみ行われています。
病気があるかどうか、またどんな病気かわからなければ治療はできず、放射線検査を受けないことによって 病態を悪化させてしまうリスクがあるということも忘れてはなりません。
よってその放射線検査が患者さんにとっていかに必要不可欠かという事を理解していただくことが非常に重要となっています。
被ばく線量低減についての取り組み
当院では放射線検査による被ばく線量が適切であるかどうか定期的に測定し関連学会のガイドラインを参考に被ばくの低減に取り組んでいます。
検査時には診療放射線技師が患者さんの体格や状態によって診断に必要な範囲に適正線量を照射することで被ばく低減に努めています。
また、患者さんごと、検査ごとに線量を記録しお問い合わせにお応えできるよう体制を整えているところです。
当院で使用している放射線機器につきましても始業前点検、終業時点検、定期点検を行い品質管理徹底に努め安心して検査を受けていただけるよう取り組んでいます。
よくあるご質問
Q 妊娠に気づかず腰椎の写真を5枚撮影した後、妊娠とわかりました。胎児の被ばくは大丈夫でしょうか?
A 生まれてくる子供に形態異常や発育が遅かったりするのではないかと心配していることと思いますが、いずれの影響も心配はいりません。
妊娠2週から8週の赤ちゃんは、確定的影響(形態異常)に対して敏感な時期ですが、放射線検査をしたと言うだけで、受けた線量に関係なく不安に駆られるお母さんが多いことを痛感しています。
しかし、腰椎のX線写真を5枚撮ったとしても胎児が受ける線量は、5mGy程度です。
したがってX線検査が原因で形態異常や低体重のお子さんが生まれてくることはありません。
Q 以前胸部写真を撮った病院では、腹部を鉛エプロンでガードしていただきましたが、今回は何も防護はありませんでした。
患者が多くて忙しいのはわかりますが、一人一人にきちんと対応していただけると有難いです。
A 撮影中に十分な説明がなされなかったため、不安を抱かせてしまい申し訳ありませんでした。
胸部写真の撮影時に腹部を鉛エプロンで遮蔽するという行為は数十年前に推奨されていたものです。現在は胸部写真で腹部が直接被ばくする事は考えられないので、必要のない防護はかえって放射線は危険との考えを増大させるという理由で鉛エプロンの使用を控える施設が多くなっています。
そもそも、胸部撮影の放射線量は表面の最大線量でも1mGyを超えることはありませんので実効線量を計算で見積もっても0.05mSv以下となります。100mSv以下では放射線の影響を考慮する必要はないというICRPの勧告もありますので、あまりにも少ない被ばくを心配する必要はありません。
大事な検査は安心して受けていただければと思います。
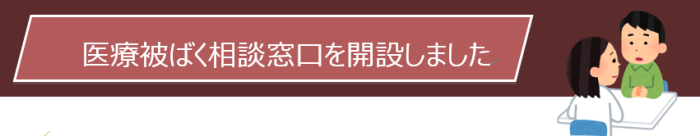
放射線検査を受ける際に不安なことや疑問などはありませんか?
中央放射線部では、当院を受診されている患者様及びそのご家族の方に安心して検査を受けていただくため、医療放射線被ばく相談を予約制にてお受けいたしております。
放射線検査についての不安や疑問に、診療放射線技師が丁寧にお答えします。
相談をご希望の方はお気軽にお申し出ください!
ご案内
| ご相談の申し込み | 総合画像センター受付 ・TEL:0859-33-8181(代表) |
|---|---|
| 場所 | 医療相談室 |
| 相談時間 | 月曜日~金曜日 9:00~16:00(12:00~13:00の間は除く) |
| 対応者 | 医療被ばく相談担当診療放射線技師 |
ご利用にあたっての注意事項
- ご相談内容によっては回答にお時間がかかる場合があります。
- ご相談いただくにあたり原則として個人情報を公開することはいたしません。
- 画像センターへの直接のお電話での相談は承っておりません。
- 患者さまの病状説明および診断に関する質問にはお答えできません。